
|
「(和歌は)力をも入れずして天地(あめつち)を動かし………」 現代において、文学はわれわれがふだん生活をしている物理的空間の外にある隠喩的空間に発生すると考えられている。だれもがテレビドラマは虚構であることを理解し、虚構が現実を侵犯する危険はないと信じている。しかし近代以前において、隠喩的空間と物理的空間は地続きだった。詩は、ときには疫病の猛威を鎮め、ときには国家事業を成功に導くテクノロジーでもあった。古人は、力を入れずに対象に作用を及ぼす言葉の不思議な力に、驚きと感動をもっていた。今日、言葉のそのような豊かさは、すっかりやせ細ってしまったように思われる。 しかしいま、「力を入れないのに対象を動かすことができる」という表現は、われわれをとりまきつつある電子的なメディアにそのままあてはめることができる。現在、物理的空間と隠喩的空間を融合させているのは、ディジタルテクノロジーである。情報ネットワークは、長い間凍りついていた隠喩的空間を再び解凍し、われわれにその豊かさをもたらしてくれようとしている。同時にわれわれは電子的メディアの中での新しい体験の原型を、古人の表現活動のなかに発見することができる。 われわれのプロジェクト「連画」は、そのような古典と現代の接合する地点で発想された。 |
|
|
この刺激的な遊びを組織的な活動とするために、1992年の4月、私は中村にある創作の方法を提案をした。まずAがきっかけになるCG作品を完成させ、それをBに電子メールで送る。Bは、Aの手元の作品と完全に同じディジタル画像のコピーを受け取る。Bはそのデータをベースに、一部を加工したり、引用したりして、B自身の作品を完成させ、再びAに送り返す。このやりとりを繰り返すことによって、絵巻物のような作品の鎖を作れるはずだ。私はこの方法を、中世に流行した和歌の集団創作ゲームである連歌の発音に倣って、連画と名付けた。RENと発音する漢字 |
連歌は14〜5世紀に大流行し、しだいに形式化し衰退していったが、俳諧の連歌(いわゆる連句)として息をふきかえし、17世紀に松尾芭蕉によって高い完成の域に達した。芭蕉は集団創作である連歌のコンダクターとしても、また発句(いわゆる俳句)を詠むソリストとしても高く評価されているが、芭蕉自身はつぎのような感想をもらしていたということが師弟の記述によって明らかになっている。 「自分は、発句の作者としての評価が高いが、自分の創作活動の中心になるのは連歌なのだ」 このことは、当時の人々にとっても意外だったようだ。19世紀の歌人、正岡子規は、芭蕉の連歌は文学ではないとまで言い切っている。芭蕉の文学は、ソリストとして作られた俳句だけで十分足りるというのだ。 そのように連歌は、芭蕉の時代から個人の創作より一段低く見られる傾向にあった。それは、芸術的な表現は作者の孤独なモノローグでなければならないという通念のためだと思われる。作者は侵すことのできない孤高の場所にいて、彼にとって他者の力を借りることは、彼の個性を薄めることであると、誰もが少なからず思っている。 一回目の連画セッションで、われわれもまた「作品は作者の所有物である」という思考からなかなか自由になれなかった。1992年4月の約一か月間に創られた三往復六作品を振り返ってみると、われわれは相手の作品から情報を削除することに躊躇し、しだいに情報が蓄積し飽和していくのがよくわかる。 |
|

|
1992年の秋、私は作品と作者の関係を問い直すために、ある実験を試みた。友人の寺門孝之は、さまざまな電子メディア、新しい素材、古い時代の画像などを縦横に用い、彼独特の雰囲気をもった作品に仕上げていく画家で、その才能は広く認められている。彼の作品に、"TRANSGENIC ANGEL"と題されたシリーズがある。私はそのなかのある作品の一部分をスキャナーでディジタイズした。
彼がコピーマシン上の一瞬の動作で作り出すディストーションを模倣するコンピュータプログラムを作り、ディジタイズした画像データを処理した。私は自分の手元で、彼の作風に似た、彼が作ったかもしれない作品が生まれたことを確信した。 その作品を彼の作品群とともにバインダーで綴じ、彼のアトリエに向かった。ニコグラフで著作権に関するレクチャーを担当していた私は、彼に著作権についてのインタビューをする名目でビデオカメラを向け、そしてバインダーを彼に手渡した。 |

|
「自分の作品が、浄化されてここにあると感じた。ぼく自身では、そこまで浄化できないんだ。作品が印刷物になって姿を変えるときに感じるのと同じような、気持ちの良さを感じる。それはいったいどこからくるのかわからない、なにも土台がない、根拠の無いなつかしさだ。」 自分の作品が自分でさえ手に負えない推進力をもち、他人の手元で変化していく楽しさを、われわれは連画の作業を通して実感していた。寺門氏の反応は、引用する快楽だけでなく、引用される快楽について考える契機になった。 たとえば身体を触ったり触られたりすることは、状況によっては不愉快であり、状況によっては快楽をもたらす。われわれは不愉快を回避するルールとして、著作権という制度を発明したが、それは同時に触りあう快楽を自閉的な衣装の外に追い出すしくみであったかもしれない。ディジタルメディアはいま著作権という制度の無効性を暴きはじめているが、それと符合するように、ディジタルメディアは引用の快楽を増幅しはじめているとも言えるだろう。 |
| われわれの第二のセッションは、同じ年の暮に始まり、今度は私が最初の一歩を踏み出すことになった。私はその意味の通り、踏み出そうとしている自分の足の写真をディジタイズし、中村に送った。中村は画像をプリントし、それにブルーのインクで加筆し、再びスキャナでディジタイズした。私は、その空から突き出したような足を渦巻状に変形し、「全自動洗濯機と熟練について」というタイトルをつけて返した。 そのようにして第二のセッションは、より自由で多様な変化を目指すという暗黙の合意の中で、ダイナミックに展開しはじめた。 日常生活の中で拾ったテキストや画像がはめ込まれることもあった。画像の一部をほかのものに転換するという手法も頻繁に用いられた。また画像の引用ではなく、三角形から三美神というように概念的に連結したり、ボッティチェリの作品「春」をお互いが念頭において展開する部分もあった。 |
|
 |
その制作過程で、中村理恵子が私にあてた一通の電子メールは、連画の意味を考える上で示唆に富むものであった。 『連画をやってるとき、自分と相手じゃなくて、自分っていう一人と、連衆としてのもう一人の私がキャッチボールをしていると思う。だから、むしろ、連衆につながって何かをするためには、強烈に自分に向き合い、自分に対していないと、できないことに気づく。連衆につながるってことは、、実はかえって、すごく個人の創作でありうる。ひとりで自分の絵を描いていると、なぜか、他人から投影された部分や、記憶が挟み込まれてきて、「あ、これは、**ちゃんの青だ、、」とか、フっと気づくときがある。個人での創作は、ともするといろいろなものを小さく切り刻む作業になる。しかし、連衆であるときは、最初から、他がまじって作品がやってくる。その時、自分と他人を分けることからは、決してなにも始まらない。それごとまるごと飲み込んではじめて、オリジナルな自分のものにしてしまうことができる。』 |
| われわれは連画を通して、自分らしさというものが決して自分という単一の枠に閉じこめられた特質ではなく、また他者は自分自身の中にもいることを発見した。
われわれはしばしば、連画のコラボレーションは、二人の人格の融合による仮想の人格による創作ではないかという指摘を受けた。たとえば企業や国家といった共同体が、あたかもひとつの人格として振る舞うように。 しかしわれわれは連画の制作過程で、二人のユニットが一つの人格を形作るという感覚を、まったく持たなかった。自分の手元にある作品は、そのなかにどんなに他人の要素が入り込んでいても、他人との共有物ではなく、あくまで自分の作品と考えた。人格が解け合って巨大な人格が立ちあらわれるという考え方は、創造をする上で決して居心地のよいものではなかったからだ。 われわれはむしろ、自分の中に多くの他者の声のポリフォニーを聞いた。非常に孤独なモノローグだと信じられている創作が、実は自分の中の多くの他者とのダイアローグによって遂行されていることを実感した。自分らしさを、自分の固い殻の中にある他人らしくないものの集合として捉えていた私にとって、これは革新的な事件だった。 おそらく連歌という発明は、近代的な自己という装置が確立する以前の、自己とコミュニティーとの自然な相互作用を様式化したものだと考えられる。ディジタルメディアとネットワークコミュニティーは、単一の構造に固定化された人格の境界線を、無垢な状態に回復する力をもっている。それは新たな自己同一性の喪失をもたらすかもしれない。が、われわれにとってより自然で、なつかしいセルフイメージに出会う契機でもあるはずだ。 |
|
|
(モンテカルロ IMAGINA'94 におけるレクチャー)
|
|
|
|
 by Nakamura
by Nakamura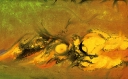 by Anzai
by Anzai はlinkを意味する。
はlinkを意味する。 はpoemを意味する。おなじくGAと発音される漢字
はpoemを意味する。おなじくGAと発音される漢字 は、pictureを意味する。歌を画に置き換えて、連画という言葉が生まれた。
は、pictureを意味する。歌を画に置き換えて、連画という言葉が生まれた。