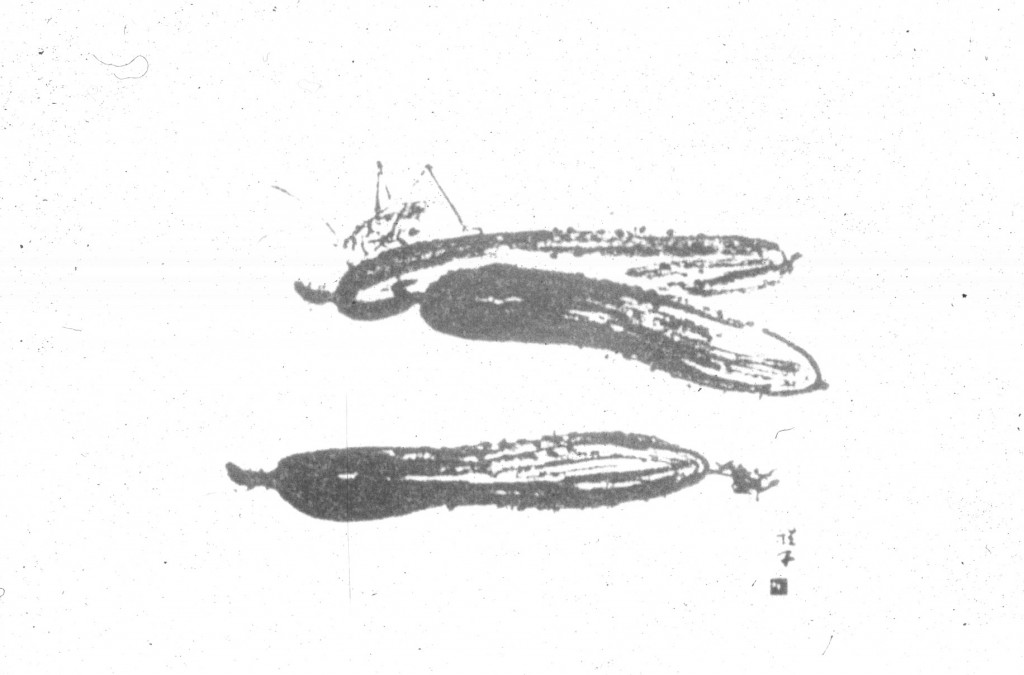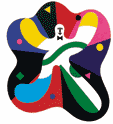カラー画像がデジタルデータとして扱えるようになりはじめた1990年代に、イメージの著作権をめぐるさまざまな議論が沸きあがった。他人の作品から新しい創作物を作る連鎖である「連画」をはじめていた関係で、僕は著作権をめぐるシンポジウムなどに何度も呼ばれた。当時の論点は、たとえばクリエイティブコモンズなどに受け継がれていく一方で、デジタルの「来航」に衝撃を受けたそのころに掘り下げた問題の本質は、むしろ風化しているようにも感じる。
当時発表に使ったスライド(ポジフィルム!)を、押入れの奥から発掘した。
◆
当時人気だった伊藤方也氏の水墨画を使った広告。
これに対してホンダのこの広告が剽窃でないかと問題になった。
微妙なのは、水墨画の古いお手本にこのような定型があること。
◆
Cマガジンの読者にとってなつかしい秋山育さんのイラスト。このスタイルに似たイラストが新聞広告に使われ、秋山さんからの抗議を受け、アートディレクターとイラストレーターが広告で謝罪することになる。
◆
下田義寛氏の院展出品作品「風舞う」(1979)。この作品がエリオット・ポーターの写真の盗用でないかと問題になった。NHKのニュースでは、両方の輪郭を画面上で重ねて完全に一致させるなどした。(下田氏はその後、作品の素材となった複数の写真家と交渉し著作権問題をクリアしている)
◆
剽窃と呼ばれたこれらの例は、仮に連画のなかで行われればまったく異なる評価軸に晒される。連画は、他人の作品のイメージそのもの、スタイル、技法などを借用しながら、それをいかに転じたかを競うゲームだ。コンテキストをすげかえるためには、明示的に盗まねばならない。連画は、人間がミームをブートストラップする雛形を提示している。複製と転義は、いわば進化のデザインパターンなのである。
著作権は、知財の権利、作者の人格権など複数のレイヤーからなる問題で一筋縄ではない。例にあげたイラストレーターは、いずれも「新聞を見た知人がみな自分の作品だと思ったようだが、自分はこんな下手でない」という自分のブランドイメージの毀損について抗議しているのであって、それには共感できる。
しかし連画的な視座からすると、作者の人格権にもまして守られるべきは「作品の人格権」だ。ポーターが撮った鳥の形態は、絵画化されたがっているのではないか、絵画化される権利が作品にはあるのではないか、と考える。これを法律として明文化するのは難しいが、生成的な借用には寛容でなくてはならない。そういう暗黙の合意がない文化は、システムが閉じてしまう。逆に、情報を劣化させる非生成的な「ぱくり」は、糾弾されるべきだ。
そういう意味で、オリンピックのエンブレムをきっかけにするデザインの剽窃問題は不当な炎上だ。それを拡散しているメディアの意図的な情報劣化のほうが、よほど気になる。